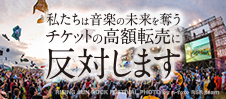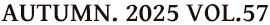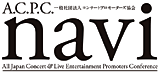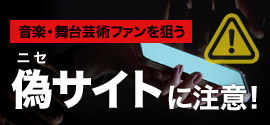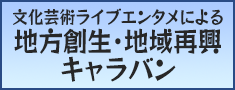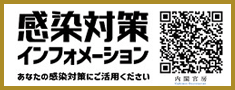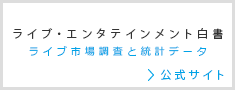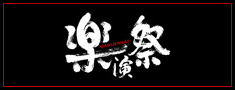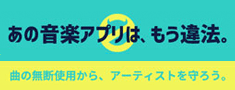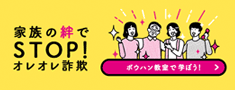取材・構成:君塚太
撮影:小山昭人(FACE)
収録日:2025年10月21日
今号の中西会長連載対談が行われたのは、太宰府天満宮(福岡県太宰府市)です。菅原道真公がお鎮まりになる御墓所の上に御社殿を戴き、全国天満宮の総本宮として知られる地を中西会長が訪れた理由は――太宰府天満宮では、これまでライブの開催を含めたアーティストとのコラボレーションが行われ、境内などに現代美術を展示するアートプログラムも実施されています。文化・芸術・芸能における様々な試みによって、地域に根づいた存在であり続けているのです。太宰府天満宮にある樹齢1500年を超える樟(くすのき)の前で写真を撮影した後、対談はスタート。全国のコンサートプロモーターにも参考になる、地域とともに歩んでいくためのヒントを、菅原道真公から数えて40代目に当たる西高辻󠄀信宏宮司と探しました。
中西:太宰府天満宮には菅原道真公が祀られていて、学問の神様というイメージがありますが、文化や芸術の神様でもあるそうですね。
西高辻󠄀:菅原家はもともと学者の家系で、道真公のお父様もお祖父様も文章(もんじょう)博士という学問の最高位の役職をお務めになりました。道真公自身も33歳の若さで文章博士になられ、政治家・詩人としてもご活躍され、漢詩や和歌も創作されていたのです。詩歌というものは、つくり手の言葉に対する思いが強く表れます。道真公がつくられた作品はほとんどが現存していますので、後世の人々にもその思いが伝わっているのだと思います。また、道真公は中国の作品を踏まえつつも、自らの言葉で漢詩の表現をされていて、内容的にも技術的にも最高峰のものであると評価されていますので、今日まで文化の面でも崇敬を集め続けているのではないでしょうか。
中西:今のような情報量がなかった時代に、もともと中国の文化であった漢詩を自分の表現として身につける感性はどこで磨かれたのでしょうか。
西高辻󠄀:幼少期から様々な書物に触れていたのでしょう。印刷もコピーもない時代ですから、書物は全部書き写して継承されていったのだと思いますが、代々それが蓄積されていき、道真公も書物に触れるようになった。学術面で成果を上げて、朝廷に仕えるようになると、学びの機会がさらに広がるという環境もあったのだと思います。
中西:その蓄積が40代にわたって引き継がれて、現在は宮司が音楽をはじめ文化・芸術にも関わっていらっしゃいますが、サカナクション山口一郎さんとの交流(太宰府天満宮の夏の天神まつりで「新宝島」「怪獣」を歌唱、太宰府天満宮案内所で流れるオリジナルサウンドも制作)は、何がきっかけで始まったのでしょうか。
西高辻󠄀:もともと山口さんのことは存じ上げていましたけれど、お会いするようになったのは、武蔵野美術大学教授でインテリア・デザイナーの片山正通(ワンダーウォール代表)さんがきっかけです。片山さんは当宮が兼務している宝満宮竈門(ほうまんぐうかまど)神社のお守り授与所をデザインしてくださった方ですが、サカナクションのライブに行かれて感動したそうで、2015年に「山口さんを太宰府に連れて行きたい」とおっしゃったんです。ちょうど、ももいろクローバーZのライブを都府楼跡(大宰府政庁跡)で開催した頃で、山口さんはそのタイミングでいらっしゃるはずが難しくなってしまって、後に改めて来てくださいました。天満宮をはじめ、太宰府の史跡そして福岡市内へ私が運転する車で足を伸ばして、2人で長時間お話したのが最初でしたね。同じ1980年生まれという共通点もありましたが、言葉にも重きを置かれている方だということが分かって共感しました。
中西:確かにサカナクションの楽曲は詞も素晴らしいですよね。